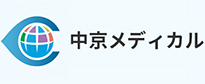令和6年度病院指標
医療の質指標
病院指標
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 63 | 37 | 88 | 74 | 122 | 235 | 439 | 987 | 1101 | 550 |
上記表は、当院に入院された患者さんのうち、2024年度に退院された患者さんの人数を10歳刻みで集計した値です。
当院は、浅間山の南のふもとに広がる地域の中核病院として、質の高い医療を幅広い年齢層の患者さんに提供できるように努めています。患者総数は3,696人で70・80歳代が最も多く、全体の56%を占めています。平均年齢は約74.0歳でした。 前年度と比較して、患者総数は107人増加となっています。その中でも、80歳代の患者が134人大きく増加しました。また、60歳以上の患者の割合が約8割を占め、地域社会の高齢化を反映していることが分かります。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし | 59 | 23.31 | 20.78 | 1.69% | 87.58 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 47 | 20.70 | 16.40 | 2.13% | 86.77 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 36 | 13.14 | 13.66 | 0.00% | 80.53 | |
| 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 2.93 | 13.07 | 0.00% | 33.20 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 24 | 20.29 | 17.33 | 4.17% | 86.79 |
当院では高齢者施設からの紹介も多く、地域の高齢化率も高くなり、嚥下機能低下を一因とする誤嚥性肺炎の症例が多くなっております。絶食補液抗生剤投与等で改善を図り、リハビリスタッフと協力して残された嚥下機能で在宅復帰できるよう工夫し、嚥下困難な症例に緩和ケアも含めて治療方針の見直しなどの検討を行っております。
当院の診療圏は高齢者の割合が多く、特に高齢女性の場合, 発熱や体調不良の原因が膀胱炎に端を発した尿路感染であることが多くみられます。また、前立腺に問題を抱える男性高齢者も増えてきており、やはり、尿路感染症を起こしやすいようです。発熱はまず内科で診察することが多く、診断の結果が尿路感染症であった場合、内科で治療を開始し、泌尿器科と連携して治療を継続し再発予防につとめることが多いです。
外食産業の発達の影響もあり、核家族生活や独居の症例は食事内容や病気の管理も自己判断で偏りやすく、糖尿病に陥りやすくなっています。普段は自覚症状も出にくいため、定期的な治療を怠るせいか、糖尿病の治療管理が不十分となり、ケトアシドーシスの症状が出たときだけ救急要請等で受診を繰り返すケースもあります。そういった症例の数は少なくても繰り返す事が多く、糖尿病性ケトアシドーシスの延べ患者数も増えているようです。
さらに、高血圧や糖尿病等を持病に抱えながら年齢を重ねる事により、心不全を発症し入院加療が必要な状態に陥る場合も多くみられます。内分泌内科チームや循環器内科チームと連携して、一般内科でも心不全症例の対応を行い治療及び再発予防につとめております。
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 63 | 6.98 | 4.54 | 0.00% | 70.95 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 12.74 | 8.88 | 2.94% | 76.85 | |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 11.28 | 9.08 | 3.13% | 69.81 | |
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 16 | 10.19 | 9.77 | 0.00% | 72.44 | |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 15 | 6.40 | 5.99 | 0.00% | 60.53 |
鼠径ヘルニアは高齢化しており、発症から時間が経過した大きなヘルニア嚢が増えています。
既往に心血管系や脳梗塞があり、術前検査や内服の調整が必要な症例が増えて、そのなかでも、超高齢者や抗凝固剤を内服している総胆管結石性胆管炎の症例が増加しており、近隣の病院で緊急内視鏡下ステント留置術が可能な施設が少ないため、当院に集中していると考えられます。
さらに、高齢化による開腹手術既往症例が増加しているため、術後癒着性腸閉塞患者が増多傾向にあります。
また、転院症例は、手術中で対応できない症例を近隣の病院へ紹介搬送しています。乳癌症例は、検診でフォローアップ中の患者が多く、その中でも病期分類ステージⅡでの症例が多いです。急性胆嚢炎発症の72時間以内の症例は手術を選択しますが、都合により、麻酔科医不在の場合は、経皮経肝胆嚢ドレナージ術を施行して後日手術予定としています。
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 70 | 20.20 | 17.33 | 4.29% | 86.46 | |
| 050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 62 | 4.90 | 4.47 | 0.00% | 70.76 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 34 | 24.62 | 16.40 | 2.94% | 86.35 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 31 | 27.42 | 20.78 | 6.45% | 89.13 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 23 | 16.13 | 13.66 | 0.00% | 82.96 |
全国的な心不全患者数増加の影響を受け、当院でも心不全入院数が増加傾向です。基本となる治療をしっかり行い、原因となる疾患をみつけるための検査を行います。一般的な治療で対応しきれない症例については、両心室ペーシング(心臓再同期療法)・経皮的僧帽弁クリップ術・経カテーテル大動脈弁留置術など最新の非薬物治療の適応を考慮して、高次医療機関に転院していただく症例も増加しています。
また、高齢化社会で増加する肺炎・尿路感染については、一般内科疾患として循環器内科でも多数受け入れをしております。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 96 | 54.41 | 25.29 | 3.13% | 83.76 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 22 | 37.00 | 19.16 | 9.09% | 79.68 | |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 22 | 4.32 | 5.95 | 0.00% | 73.82 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 17 | 39.59 | 18.76 | 0.00% | 69.94 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 16 | 37.19 | 21.38 | 0.00% | 75.25 |
骨粗鬆症に伴う骨折と人工関節手術が入院患者数の上位を占めています。人口高齢化に伴って、骨折と変形性関節症は増加しています。大腿骨近位部骨折に対して二次性骨折予防継続管理料が設定されました。大腿骨近位部骨折を受傷し手術が必要となった場合、入院中から骨折予防を開始し、外来で骨粗鬆症治療を継続していくことが求められています。大腿骨近位部骨折を受傷した場合、1年以内の骨折発生率が高いことと、骨折後の寿命が短くなることが明らかとなっているからです。骨折の治療、リハビリテーションに限らず、入院中より二次性骨折予防継続管理を実施し、外来で骨粗鬆症治療を継続します。入院から外来まで連続的な治療ができるように二次性骨折予防継続管理を組み込んだ大腿骨近位部骨折観血的手術のクリニカルパスを作成・運用していきます。
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 302 | 2.01 | 2.49 | 0.00% | 75.63 | |
| 020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 24 | 2.08 | 4.52 | 0.00% | 74.42 | |
| 020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | – | – | 5.47 | – | – | |
| 020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | – | – | 4.83 | – | – | |
| 020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 5.58 | – | – |
白内障術前後のフォロー、屈折矯正、緑内障に対する点眼・レーザー・手術治療、網膜硝子体疾患として動静脈閉塞、糖尿病合併症、網膜剥離や黄斑円孔などの緊急手術を要する疾患を取り扱っています。硝子体注射や緊急手術なども対応しています。
そのほか、ぶどう膜炎や斜視、角膜疾患等の診療も行っており、眼科の初期対応から緊急疾患まで幅広く対応しています。角膜移植や涙道の手術治療については、適宜診察しながら必要なタイミングで紹介を行います。
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 54 | 25.00 | 16.89 | 1.85% | 74.87 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 35 | 13.94 | 9.83 | 0.00% | 78.17 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 15.53 | 7.99 | 3.13% | 74.31 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 52.41 | 18.68 | 4.55% | 73.36 | |
| 010060xx99x41x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 12 | 36.00 | 29.66 | 16.67% | 90.75 |
〈脳梗塞について〉
当院では脳神経外科・脳神経内科で脳卒中チームをつくり、24時間体制で診断・治療をおこなっています。超急性期には適応があればtPA治療(急性期再開通療法)をおこなっています。内頚動脈、中大脳動脈など太い動脈の血栓症に関しては、外部より血管内治療医を招聘し行っています。
慢性期リハビリテーションは地域包括ケア病棟、あるいはリハビリテーション専門病院の回復期病床と連携をとり行っています。2023年9月より回復期リハビリテーション病棟が開設され、急性期の治療後、自宅や社会に戻ってから日常生活を送れるようにリハビリを専門に行っています。
〈外傷・非外傷性による脳出血について〉
脳出血の中で、最も多い慢性硬膜下血腫に対しては、局所麻酔下で穿頭血腫除去術を施行し、頭蓋内血腫に対しては、全身麻酔下による開頭血腫除去を施行しています。急性外傷、疾患によって、手術が必要であれば緊急手術を行っています。
〈てんかんについて〉
当院のてんかんの治療は、基本的に神経細胞の異常興奮を抑える作用を持つ抗てんかん薬の内服治療が行われます。多くは抗てんかん薬の服薬を続けることで、てんかん発作を抑制することができ、通常の社会生活を送ることが出来るようになります。
脳神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 29 | 38.76 | 16.89 | 10.34% | 78.52 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 22 | 18.55 | 16.40 | 0.00% | 85.59 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 21 | 25.33 | 20.78 | 4.76% | 84.48 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 17 | 27.29 | 13.66 | 5.88% | 81.76 | |
| 010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 17.95 | – | – |
脳梗塞:当院では脳外科医師との脳卒中オンコール体制で24時間365日の脳卒中診療体制をとっております。急性期治療だけでなく、リハビリを当院で継続して行う場合があり、患者さんや家族が希望すれば期間に余裕をもってリハビリを行うことも行っております。
尿路感染症:高齢者の尿路感染症の場合は、感染症による廃用が進む場合もあり、入院後にリハビリなども行う形をとっています。
誤嚥性肺炎:神経難病患者の在宅診療や脳梗塞後の患者さんを診療する機会も多く、ご高齢な方の誤嚥性肺炎での入院も多くなっています。
心不全:当院の診療圏は高齢者の割合が多いため、高血圧や糖尿病等を持病に抱えながら年齢を重
ねると、心不全で入院加療が必要な状態に陥る事も多く、内科チームや循環器内科チームと連携し
て対応し、治療及び再発予防につとめております。
パーキンソン病:高齢の方は疾患の進行と共に生活を変える必要があり、安全の面からのアドバイスもしています。介護保険の導入、リハビリ、身障の申請なども行っています。訪問診療している神経難病患者は個々の患者さんに応じてレスパイト入院にも対応しており、在宅療養を継続する助けとなれば良いと考えております。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 55 | 2.15 | 2.45 | 0.00% | 73.96 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 30 | 9.33 | 6.81 | 0.00% | 76.67 | |
| 11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 16 | 2.81 | 2.40 | 0.00% | 65.88 | |
| 11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | – | – | 7.95 | – | – | |
| 110080xx97x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | 11.98 | – | – |
前立腺癌疑いの患者さんを対象に確定診断目的に前立腺針生検を行っております。
通常入院は1泊2日を予定しています。検査後は出血・痛み・感染のコントロール・排尿障害の有無を観察し合併症対策に努めております。
膀胱腫瘍に対する初期治療として経尿道的手術を行っています。
通常入院日数は8日を予定していますが、病状が安定している患者さんには早期退院をおすすめします。また、合併症のある患者さんには安全な手術を遂行できるよう入院術前管理を行い、術後は各患者さんが安心して退院できるように排尿状態が安定するまでの入院を提供しています。
自然排石が難しい腎尿管結石に対して体外衝撃波結石破砕術を行っています。
予定入院日数は2日ですが術後の結石による痛みや尿路感染がある場合は、病状が安定するまで入院管理しています。
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| 0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 17 | 3.18 | 5.61 | 0.00% | 5.06 | |
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 10 | 2.90 | 6.11 | 10.00% | 0.00 | |
| 040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | – | – | 6.98 | – | – | |
| 180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし | – | – | 8.02 | – | – | |
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 6.38 | – | – |
令和6年度の急性期感染症については、新型コロナウイルスの感染流行がほぼ落ち着いた一年でした。その反面、従来の流行性感染症が増加傾向を示し、夏期にRSウイルス感染症の流行が早期に始まり、手足口病、ヘルパンギーナ、アデノウイルス感染症といった夏期特有の流行性疾患が多くみられました。
冬期ではインフルエンザも年度末を中心に大流行を認めました(3位)。したがって、入院治療患者の割合は上記ウイルス疾患にともなう肺炎が増加し(1位)、またRSウイルス感染に伴う喘息性疾患も(5位)入院対症となる患者数が増加しました。しかしながら、ワクチン定期接種により水痘、ロタウイルス胃腸炎はほとんど経験しませんでした。
小児では、急性期疾患が例年上位を占めますが、新生児関係の診療も多い部類に入ります。院内分娩取り扱い数は例年平均よりは減少しておりますが、急激な落ち込みは無く、分娩数も徐々に回復してきた印象でありました。目立った重症新生児はみられず、院内感染も無く安心安全な分娩の一年でありました。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類基準 | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage -I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 大腸癌 | – | 25 | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 肝癌 | – | – | – | – | – | 27 | 1 | 8 |
胃癌:全国的に胃癌症例は減少傾向にありますが、最近は初診時から肝転移や腹膜播種による手術適応外の症例、超高齢者の化学療法の適応外症例が増えています。
大腸癌:大腸癌は増加傾向にありますが、これも高齢化しており、病期分類ステージⅢ以上が25%で、再発のリスクが高い症例で手術+化学療法で加療を行っています。
乳癌:二次検診の経過観察からの発症が多く、病期分類ステージⅡ以内が86%となっています。術後ホルモン療法や化学療法を行い、昨今10年以上経過してからの再発症例が増えています。
肺癌:現在、当院では手術を行っておりません。螺旋CTによる肺癌検診を行っており、発見した場合は、近隣の病院へ紹介し手術となっています。
肝癌:B型肝炎やC型肝炎が無い患者でも発見される症例が増加傾向にありますが、高齢者や肝硬変症例が多いことから、肝動脈塞栓術や経皮経肝ラジオ波焼灼術が多く行われています。肝細胞癌は再発が多いため、反復治療を繰り返し行われています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 18 | 10.44 | 47.72 |
| 中等症 | 100 | 20.80 | 82.29 |
| 重症 | 31 | 20.94 | 87.48 |
| 超重症 | – | – | – |
| 不明 | – | – | – |
仕事や日常生活での無理がたたり、喫煙や飲酒もひきがねとなった働き盛りの中高年の肺炎患者も一定数あり、そのような肺炎は軽症であることが多く、入院安静や禁酒禁煙で比較的短期間の入院で軽快し退院されます。
その一方で、肺炎の主体は高齢者で、加齢による嚥下機能低下や呼吸機能低下により喀痰排出能力が低下し、重症化してから受診されることも多くなっています。このような症例は入院後も治療に難渋し入院期間が長引くことが多いのが現状です。そのような高齢者も肺炎治癒をめざし、治癒後もリハビリ等で在宅復帰を目指しております。
そのため、一般的に重症になれば治療にもリハビリにも時間がかかり、重症症例ほど入院日数が長くなり、年齢も高齢になるほどより重症となる傾向があるようです。
脳梗塞の患者数
| ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 146 | 36.36 | 78.75 | 9.33% |
| その他 | – | – | – | – |
一過性脳虚血発作は受診時に症状が消失していることが多いですが、48時間以内の再発率が高いことから数日入院し、検査、治療を開始しています。
当院では脳神経外科・脳神経内科で脳卒中チームをつくり、24時間体制で診断・治療をおこなっています。超急性期には適応があればtPA治療(急性期再開通療法)をおこなっています。
内頚動脈、中大脳動脈など太い動脈の血栓症に関しては、外部より血管内治療医を招聘し行っています。
慢性期リハビリテーションは、地域包括ケア病棟、あるいはリハビリテーション専門病院の回復期病床と連携をとり行っているため、リハビリテーション専門病院への転院が大部分を占めています。2023年9月より回復期リハビリテーション病棟を開設しました。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 62 | 4.53 | 47.75 | 3.23% | 81.74 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 49 | 6.71 | 46.35 | 2.04% | 82.41 | |
| K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 等 | 42 | 2.21 | 13.50 | 0.00% | 68.21 | |
| K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 等 | 33 | 3.94 | 33.76 | 0.00% | 72.79 | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) 等 | 21 | 0.62 | 3.19 | 0.00% | 59.48 |
骨粗鬆症に伴う骨折手術と人工関節手術が手術件数の上位となっています。当院では人工関節センターを設置し、入院前のリハビリテーション、術前自己血採血を含めた入院・手術準備から、術後の外来経過観察まで、高齢の変形性膝関節症・股関節症患者にも安全に人工関節置換術が行える体勢を整えています。また、効率的医療が求められる時代ですが、効率的とは入院日数が短いということを目指すのではなく、退院時に十分な生活能力が再獲得できていることが最も効率的な医療であるとの考えに基づき、適切なリハビリテーションを実施したうえで退院を迎えられるように、術後リハビリテーションのスケジュール設定をしています。
2023年9月より回復期リハビリテーション病棟が開設され、急性期の治療後、自宅や社会に戻ってから日常生活を送れるようにリハビリテーションを専門に行っています。
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 等 | 37 | 2.19 | 5.57 | 0.00% | 69.24 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 33 | 2.03 | 7.94 | 0.00% | 64.18 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 30 | 1.83 | 9.27 | 0.00% | 77.87 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 26 | 1.00 | 2.58 | 0.00% | 69.81 | |
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 等 | 14 | 1.50 | 7.57 | 0.00% | 72.00 |
鼡径ヘルニア手術は増多傾向で、平均年齢も70歳近くまで上昇しています。麻酔方法は、局所麻酔から全身麻酔まで症例に併せた方法を選択し、クーゲルパッチ法(筋肉と腹膜の間に人工メッシュシートを置いて、穴を塞ぐ手術)を主に行われています。
前立腺手術や膀胱手術の既往がある症例は、メッシュプラグ法(ポリプロピレン製のプラグを筋膜の弱い部分に入れて出口を塞ぐ手術)で行われています。また、ヘルニアの開腹歴が無く、両側である症例は術後の疼痛から腹腔鏡手術を薦めています。
胆嚢炎の場合、検診を受けておらず、胆石があることを知らずに受診している患者が増えています。急性胆嚢炎発症の72時間以内の症例は手術を選択しますが、都合により、麻酔科医不在の場合、経皮経肝胆嚢ドレナージ術を施行して後日手術予定としています。
乳癌手術は病期分類ステージⅡまでの症例が多く、乳房部分切除+センチネルリンパ節生検の術式が一般的です。また、乳輪直下の腫瘍や乳管浸潤癌の場合は乳房全摘を行っています。
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 300 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 75.74 | |
| K2686 | 緑内障手術 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 等 | 20 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 75.10 | |
| K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 10 | 0.90 | 1.80 | 0.00% | 65.90 | |
| K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | – | – | – | – | – | |
| K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの 等 | – | – | – | – | – |
2025年7月より硝子体手術を毎週月曜に開始しました。緊急の硝子体手術も含め、より広く緊急疾患に対応できるようになりました。低侵襲緑内障手術にも引き続き対応します。
2025年9月より3ヶ月に1回の緑内障専門外来がスタートしました。現状でも、緑内障一般診療、レーザーは診療日に対応し、低侵襲緑内障手術も毎週行っておりますが、プリザーフローマイクロシャントや濾過手術について、緑内障専門医に執刀・指導をいただき3ヶ月に一度まとめて手術を行います。緊急対応が必要なものについては別途日程を調整します。
白内障については引き続き手術を行っています。強膜内固定まで施行可能なため、すべての症例について手術を行えます。なお、麻酔科医不足のため、全身麻酔が必要なものに関しては当院より紹介を行うことがあります。
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 等 | 58 | 4.33 | 2.02 | 0.00% | 73.29 | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 20 | 0.10 | 14.60 | 0.00% | 71.25 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 15 | 10.27 | 11.73 | 0.00% | 82.13 | |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 12 | 0.00 | 16.92 | 0.00% | 76.50 | |
| K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの 等 | 10 | 1.70 | 1.60 | 0.00% | 61.10 |
主に心房細動という不整脈に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術が軌道に乗り増加しております。
心筋梗塞・狭心症に対するカテーテル治療は、ほとんどが急性期のものに対して緊急で施行されており、ほぼ例年並の件数となっています。
内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 16 | 3.00 | 13.75 | 0.00% | 82.25 | |
| K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 等 | 12 | 1.08 | 8.67 | 0.00% | 71.58 | |
| K697-31ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として) 2センチメートル以内のもの その他のもの | – | – | – | – | – | |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | – | – | – | – | – | |
| K682-2 | 経皮的胆管ドレナージ術 | – | – | – | – | – |
慢性肝疾患の原因は、以前はB型肝炎、C型肝炎、アルコール性肝炎が主でしたが、近年は代謝疾患(糖尿病、脂質異常症、肥満など)を由来とする脂肪肝関連疾患が増加しています。慢性肝疾患の大きな合併症として肝細胞癌があり、手術、ラジオ波焼灼、肝動脈塞栓術(血管塞栓術)が治療手段として有用です。肝細胞癌は再発が多く反復治療を要し、血管塞栓術のニーズが高くなっています。経動脈的に抗腫瘍薬、塞栓物質を癌に注入し、壊死を図る治療手技です。
また血管塞栓術は肝細胞癌の治療手段としてのみならず、出血性疾患(消化管出血など)、腹部内臓動脈瘤の治療にも応用され、低侵襲治療としての有用性が評価されています。血管塞栓術以外の肝細胞癌の治療として、当科では肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法を行い、同様に低侵襲な治療として評価を受けています。
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 30 | 1.27 | 7.07 | 0.00% | 76.67 | |
| K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 等 | 16 | 0.31 | 1.50 | 0.00% | 65.88 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
| K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 等 | – | – | – | – | – | |
| K7983 | 膀胱結石、異物摘出術 レーザーによるもの 等 | – | – | – | – | – |
膀胱腫瘍に対して腰椎麻酔下経尿道的手術(内視鏡手術)を行っています。
予定入院期間8日、多くの場合はこの内視鏡手術で根治治療となりますが、切除しきれない浸潤性がんや転移を有するがんにおいては追加治療を高度医療機関に紹介致します。
自然排石が難しい腎尿管結石の治療として体外衝撃波結石破砕術を行っています。
予定入院日数は2日、必要に応じて尿管ステント留置します。
破砕効果不十分な場合は追加で衝撃波治療を繰り返し行いますが、治療効果が見られない場合は尿管鏡治療を行います。
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 27 | 0.52 | 11.48 | 0.00% | 78.19 | |
| K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | – | – | – | – | – | |
| K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | – | – | – | – | – | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | – | – | – | – | – | |
| K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 等 | – | – | – | – | – |
慢性硬膜下血腫は外傷後、慢性的(通常は3週間以降)に血腫がたまり症状を起こす疾患であり、局所麻酔下で穿頭血腫除去術を行っています。
脳内出血は高血圧などにより動脈硬化きたした穿通枝(脳内の細い血管)が破綻して出血を起こし発症するものです。意識障害、片麻痺、言語障害などが主な症状です。
発症、部位、血腫の大きさ、症状などより手術適応を判断し、開頭術(顕微鏡を使用)CT誘導下(CTを撮影しながら血腫の位置を確認しながら摘出)、神経内視鏡下のいずれから手術方法を選びます。手術後症状の回復には長期のリハビリテーションを必要とします。
脳動脈瘤は脳内の比較的太い動脈の一部がふくれて出血を起こすクモ膜下出血。あるいは、偶然にも脳検査などによって発見されます。クモ膜下出血をきたした場合は、再破裂を防ぐ為に開頭術によるクリッピング術(顕微鏡使用)、カテーテルを通して行うコイル塞栓術のいずれかの方法を状態、動脈瘤の場所などに応じて決定します。破裂していない動脈瘤の場合、経過観察を含め慎重に治療方法を決定します。
脳腫瘍は頭蓋内に発生した腫瘍をさしますが、腫瘍が大きく脳の圧迫がある症状をひき起こし、腫瘍周囲にむくみをきたしている重要神経組織、血管組織の傍に存在する場合、手術適応になることがあります。開頭し顕微鏡下で腫瘍を摘出します。
周囲には重要組織があるため脳波モニター、神経内視鏡、超音波ドプラー、術中血管造影などを駆使して行います。
水頭症手術はクモ膜下出血後と特発性正常圧水頭症に対して行っています。特発性水頭症は認知機能低下、歩行障害、尿失禁などの症状を徐々におこすもので、認知症の二次的原因疾患の一つです。シャント手術により認知機能低下、歩行障害、尿失禁に改善が期待できます。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 11 | 0.30% |
| 異なる | 13 | 0.35% | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 0.41% |
| 異なる | – | – |
〈内科〉
内科領域の疾患でDIC(播種性血管内凝固症候群)や敗血症に陥る症例は、尿路感染、胆道感染等が挙げられます。高齢者だと病気の局在がはっきりせず、後から原疾患が同定されることが多いため、入院契機と同一である場合と異なる場合とが認められるようです。
真菌感染症は、自己免疫疾患で免疫抑制剤を使い続けた症例が多いため、入院契機とは異なる場合が多いと考えられます。処置等の合併症は、尿道膀胱内留置カテーテルや透析血管内留置カテーテル(テシオカテーテル)等治療に必要な留置カテーテルへの感染など、あらかじめ予想される合併症が一定割合生じています。そのため、そのまま入院契機となる事が多く、一方で当初は誤嚥性肺炎など別の診断で入院し、当初の疾患は治癒したものの、退院に向けたリハビリ中などに、上記尿道膀胱内カテーテル感染などを発症し、入院契機と異なる疾病として後日発症するケースも起きています。
〈外科〉
心不全や大動脈解離、腹部大動脈瘤を患っている超高齢者が総胆管結石症で胆管炎となり、入院後、敗血症性ショックからDIC(播種性血管内凝固症候群)へ合併する症例が増えています。
真菌血症はPPI(プロトンポンプ阻害薬)常用している逆流性食道炎患者の長期絶食や中心静脈カテーテル留置中に発症する症例があります。手術、処置後の合併症は、内視鏡下胆道処置後のERCP(内視鏡的逆行性胆道膵管造影検査)後の膵炎が最多と考えられます。術後腸管麻痺によるイレウスはありますが、再手術となった症例はありませんでした。
〈循環器内科〉
播種性血管内凝固症候群・敗血症は、多くの場合、肺炎・尿路感染症に合併しています。循環器内科の特性として、心内膜炎・感染性動脈瘤といった心血管系の感染症が少数含まれ、これらの疾病は敗血症として発症することが多く重症感染症となります。
〈脳神経外科〉
水頭症に対するシャント術は、シャントチューブが細いため閉塞することがあるので、再手術をおこない症状の改善をはかります。頭部手術で人工骨を使用することがあるので、時に異物反応をおこし感染をおこすことがあります。通常は異物を除去することで解決します。
医療の質指標
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 318 | 310 | 97.48% |
下肢骨折・下肢人工関節置換術等下肢静脈血栓症・肺塞栓症ハイリスクな患者に対しては、フットンプ使用、下肢弾性包帯あるいは弾性ストッキング装用し、下肢静脈血栓症を予防しています。 下肢人工関節置換術においては、出血性素因等なければ全例抗凝固薬の予防投与を行います。
血液培養2セット実施率
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 1048 | 889 | 84.83% |
細菌感染を原因とする疾患として、当院でも急性肺炎、急性尿路感染症、急性胆管炎、胆のう炎などの症例を多く診療しております。その他感染性心内膜炎を診療することも多くあります。これらの疾患では治療に用いる抗生剤の選択と投与期間が重要であり、その根拠として、各種培養検査が必要になります。肺炎だと喀痰培養、尿路感染だと尿培養などが重要ですが、いずれの疾患でも菌血症に陥ることがあり、そのような場合に血液培養を行います。熟練した医師、看護師等により常在菌が混入しないよう、混入しにくい部位を選び、局所をよく消毒し、清潔操作で行うわけですが、それでもなお常在菌が混入して判断に迷うことがあり、起因菌か、もしくは混入した関係の無い菌であるかを判断するために、複数回の培養を行う事が多くなっております。これも患者さんの負担が大きい場合や、病態、培養器具の供給不足等の問題もあり、必要に応じて1回に減らす場合があります。
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
| 広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 214 | 199 | 92.99% |
細菌感染症の治療において、抗菌薬投与は重要な治療手段の一つに挙げられます。抵抗力の弱い高齢者や、慢性閉塞性換気障害、陳旧性心筋梗塞、神経難病、各種癌で化学療法を行っている症例などは細菌感染症を繰り返すことが多く、抗菌薬治療をおこなう回数が増えることになり、結果として抗菌薬の効かない耐性菌による細菌感染症を起こすことも増えてきます。その場合、耐性菌にも有効な広域スペクトル抗菌薬を用いて治療することになります。
理論上、広域スペクトル抗菌薬にも耐性菌が生じる危険性があり、そうなると有効な抗生剤の存在しない病原菌が発生しかねないこととなり、治療法が無くなる事態も想定され非常に危険です。
従って、広域スペクトル抗菌薬は耐性菌の可能性の低い症例に最初から用いる事は避けて、起因菌をはっきり同定して、他に有効な抗生剤が無い場合に用いる事になります。
当院でも広域スペクトル抗菌薬は、細菌培養で感受性があることがわかった基礎疾患のある症例に用いるよう心がけております。ただし、初診時に致死的になりかねない重症例では、最初から広域スペクトル抗菌薬をもちいることもあり、その場合は抗菌薬投与前に施行した培養結果が出た時点で、広域で無くても感受性のある抗菌薬に変更することで、新たな耐性菌の出現を予防することをこころがけております。また、抗菌薬投与後に培養しても、菌が培養されない(偽陰性)事もあるため、培養を出せないケースもあります。
転倒・転落発生率
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 | ||||||
| 78,222 | 153 | 1.96‰ |
転倒・転落は病院・施設において、報告されているインシデント・アクシデントレポートの中でも、最も多い事故の一つであります。手術や長期の入院など患者の身体的、精神的負担だけでなく、医療費増加など、転倒・転落対策は重要な課題と言えます。インシデント・アクシデントレポートの分析から、転倒・転落の要因を確認し、具体的対策について医療安全チームの中で、年3回協議しております。
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上発生率
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
||||||
| – | – | – |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
||||||
| 291 | 291 | 100.00% |
当院では全身麻酔手術のほぼ全例において、執刀開始1時間以内に予防的抗菌薬の投与が行われております。手術執刀開始前1時間以内に適切な抗菌薬を投与し、執刀時に有効な血中濃度が維持されることで、手術部位の感染発生を予防できることが期待されます。
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
||||||
| 3,879 | 72 | 1.86% |
当院の入院患者は60歳以上の患者割合が約8割を占めており、浅間南麓診療圏の高齢者が多く、その中で高齢者による心不全や誤嚥性肺炎で入院する患者が多くなっています。
高齢者の皮膚は、皮下組織量の減少やバリア機能の低下がみられ、皮膚損傷を起こしやすいと言われております。病状等から浮腫などがみられることも多く、より脆弱な皮膚の状態となり褥瘡発生に繋がっています。
当院では医師、看護師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、薬剤師の多職種で褥瘡対策チームが組織されており、チームで連携して褥瘡発生予防・発生後早期からの適切な処置が行えるように活動しています。
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
| 65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
||||||
| 2,718 | 1,648 | 60.63% |
当院は他職種による栄養管理を行っています。入院後、看護師が身体計測を実施し、栄養スクリーニング(65歳以下MUST/65歳以上MNA-SF)を行います。栄養スクリーニングにより低栄養の疑いのある患者を抽出し、低栄養の疑いのある患者に対し、管理栄養士はGLIM基準(低栄養診断基準)により低栄養診断を行います。低栄養と診断された患者はNSTチームが介入し、最も適切な食事や栄養補給方法の提案や病気回復、合併症予防に有用な栄養管理方法の提案などを行っています。
医師が特別な栄養管理が必要と判断した患者に対し、管理栄養士は栄養管理計画書を作成します。栄養改善に向け、医師の指示を仰ぎながら嗜好調査、及び食事調整しながら、定期的に再評価をし、栄養改善を目指します。
身体的拘束の実施率
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 | ||||||
| 60,720 | 16,572 | 27.29% |
認知症ケアに係る医師、看護師、社会福祉士、薬剤師、管理栄養士、作業療法士等で認知症ケアチームを組織して、認知症認定看護師中心に、せん妄、認知機能低下のある患者を対象に、週1回病棟ラウンドを行っています。拘束患者の実態を把握するとともに、認知症症状の悪化やせん妄発症予防の対策を行っています。
また、病棟内にリンクナースを配置し、早期に認知症ケアチーム介入が出来るように連携し、その病棟看護師が身体拘束の患者に対して、連日拘束解除に向けたカンファレンスを行います。身体拘束最小化に向けた対策が取れるようにリンクナースが働きかけています。
拘束解除に向けた取り組みの院内研修、事例検討会等を行いながら、身体拘束の種類や期間、身体拘束実施の背景などを把握し、拘束率減少の活動に取り組んでおります。
 JA長野厚生連
JA長野厚生連